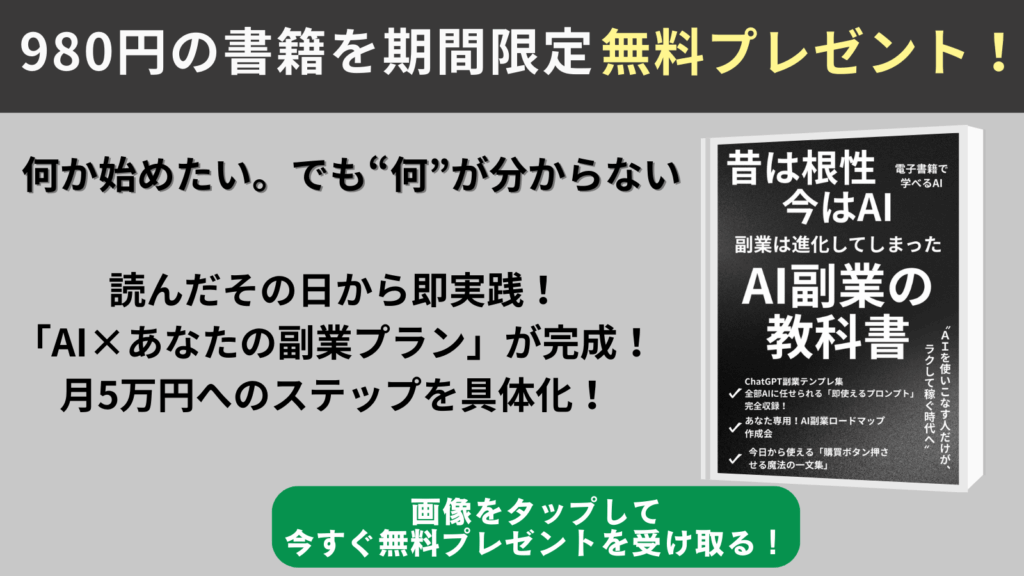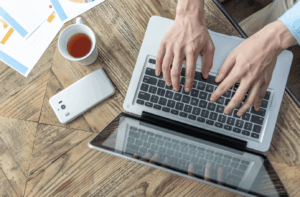「え、またAIに頼っちゃってズルくない?…ってか、最近マジで楽しそうだね!」
ある朝、妻にそう言われたんです。
子どもたちにご飯を食べさせながら交わされた、まさかの“AI雑談”。
そう返すと、妻は少し驚いた顔で「すごいじゃん。でも、それ本当に自分で書いたの?」と笑いました。
──でも僕は、笑いながらも胸の中で少し誇らしかった。
かつての僕は、夜な夜なパソコンに向かって記事を書いていた。
リサーチ、構成、執筆、校正…すべて自力。
気づけば明け方で、体も頭もクタクタ。
「このまま、いつまで続けられるんだろう…」
そんな不安が、いつも背中にのしかかっていたんです。
でも今は違う。
ChatGPTという“相棒”がいることで、僕の働き方も、感情も、大きく変わってきたんです。
“なんとなく使ってた”時代の話

実を言うと、ChatGPTの存在は知ってたんです。
でも当時の僕は、典型的な「なんとなく使ってる人」でした。
思いつきで話しかけてみたり、簡単な文章を書かせてみたり──
でも、うまく使いこなせてる気はまったくしなかった。
「これ、ホントに使い物になるのか…?」
「やっぱりちゃんと勉強しなきゃ無理かもな」
そう思って、またいつもの作業に戻っていく日々。
でもある日ふと思ったんです。
「…いや、俺、全然ちゃんと使ってないだけじゃね?」
それからいろんな記事を読んだり、活用事例を調べたり、プロンプトの構文を研究したり…
気づけばChatGPTにまつわる情報を本気でリサーチしている自分がいました。
するとある瞬間、確信に変わったんです。
「あ、これ、たった3時間ちゃんと使い倒せば、誰でも“使える人間”になれるぞ」
決意:「今、やってみよう」
ちょうどそのタイミングで、ある講座に参加する機会がありました。
内容自体も実践的で学びが多かったのですが、
特に印象に残ったのが、講師が語ったこの一言でした。
「のび太が『宿題やって〜!』って言えば、ドラえもんは完璧な道具を出してくれますよね?
でも、“何をどうしたいのか”が曖昧だと、道具の使い方もズレちゃう。
実はこれ、生成AIでもまったく同じ。
ちゃんと頼めば叶えてくれるけど、“お願いの仕方”こそが一番のスキルなんです。」

この言葉を聞いたとき、僕は思ったんです。
「そうか…ChatGPTを“使いこなす”って、こういうことなんだ」
ただ話しかけるだけじゃなくて、
“何を、どんな風に、なぜお願いするのか”を明確にできれば、
ChatGPTはまさに「ビジネス版ドラえもん」になる──。
そして僕は確信しました。
「あと3時間、本気で向き合えば、“お願いの仕方”は絶対身につけられる」
「つまり、3時間あれば“使いこなす人間”になれる」
その日、僕は予定していた作業をすべて後回しにして、
3時間、ChatGPTと徹底的に向き合うことを決めたのです。
3時間で“使える人間”になるための6ステップ
僕が「これは3時間でいける」と直感してから、
実際にやったことは大きく分けて6つです。
順番も、やることも、すべてシンプル。
でも、1つずつ着実に積み上げると、
ChatGPTが“使えるツール”から“武器”に変わるのを感じました。
ステップ①:まずは「正しいChatGPT」にアクセスせよ

驚くほど多いのが、最初からつまずくパターン。
ChatGPTを使いたい!と思ってアプリストアを開いた人は要注意。
偽物・類似・中身不明のアプリが山ほど出てきます。
「なんか変な広告付きのアプリ使ってた」 「非公式のGPTで、機能が足りなかった」
これ、マジでもったいないです。
僕も最初、変なアプリを入れて「なんか使いづらいな…」と感じていたんですが、
それ、そもそも公式じゃなかったんです。
まずやるべきことはこれだけ。
ここが出発点。
地図で言えば、まだ家を出る前の段階です。
※スマホなら公式アプリ「ChatGPT」(OpenAI提供)をDL。
“環境が整うだけで、使い心地がまるで違う”というのが体験して分かったこと。
ステップ②:1つでいい、“感動体験”を

次にやることは、何より「感動」すること。
例えばこんなふうに打ち込んでみてください。
「明日の会議は中止になりました。取引先に丁寧なメール文を作ってください」
秒で、それっぽい文章が返ってきます。
件名:会議中止のご連絡
お世話になっております。突然のご連絡失礼いたします。明日予定していた会議につきまして…
この瞬間に僕は思いました。
「うわ、やば。これ…もうビジネス文章書けるじゃん。」
「これが“使える”ってことか」と初めて理解できた気がしました。
だけど、すぐに次の感情が追いかけてきた。
「いや待てよ…これ、もし“ブログ”に活かせたら?」
「この文章力を自分の武器として磨き込めたら…副業、加速するんじゃないか?」
気づいたら、ゾクッと鳥肌が立っていた。
“文章を書く”という作業が、これまでどれだけ重く感じていたか。
「構成どうしよう」「言い回しが変」「結局、何が言いたいか分からない」
そんな悩みを、ChatGPTが一瞬で整えてくれる。
つまりこれは、“文章力の外注”なんてもんじゃない。
“思考の拡張”であり、ビジネスの加速装置だ。
そう確信した瞬間から、僕は「ブログの設計にどう落とし込むか?」をノートに書き始めていた。
ステップ③:基本の活用事例5つを“体で覚える”
ここで、もう一歩踏み込みます。
下記の5つの活用パターンは、正直“マスト”です。
逆にここを押さえずに応用にいくと、だいたい躓きます。
✅ 翻訳(英⇔日、敬語⇔カジュアル): 海外の文献リサーチで、これまで翻訳サイトをいくつも開いてコピペしていた時間が嘘のように短縮されました。「この技術、マジですごい…」と改めて感動しました。
✅ 表変換(文章 → 表、CSV → 文): 複数の記事のデータを集計する際、CSVファイルを読み込ませて分かりやすい表形式に変換してもらったり、逆に文章で箇条書きにした情報を表に整理してもらったり。これまで手作業で時間をかけていた作業が、数秒で完了する衝撃は忘れられません。
✅ 試験問題の作成(小テスト風、選択式など): これは直接的な業務ではありませんでしたが、「こんなこともできるのか!」という驚きがありました。例えば、自分が書いた記事の内容理解度を測るための小テストをAIに作成してもらうことで、AIの可能性をさらに深く理解することができました。
✅ メールや記事の下書き: ステップ②で体験したメール作成はもちろん、ブログ記事の導入部分や各段落の骨子をAIに作成してもらうことで、執筆のスタートダッシュが劇的に楽になりました。以前は数時間かけていた構成案作成が、AIとの対話を通じて30分程度で完了することも珍しくありません。
✅ 画像生成(DALL·E): これはまだ試行錯誤の段階ですが、記事のアイキャッチ画像をAIに生成してもらうことで、これまで画像素材を探す手間や、有料素材サイトのコストを削減できる可能性を感じています。自分のイメージを言葉で伝えるだけで、オリジナリティ溢れる画像が生成されるのは、本当に面白い体験です。
これらの基本を一つひとつ自分の情報発信のフローに合わせて試すことで、「こう使えばいいのか!」という具体的なイメージが湧き、AIが単なるツールではなく、頼れる相棒へと変わっていきました。
ステップ④:「なぜ嘘をつくのか?」を理解する
ここでようやく、“仕組み”の話になります。
実はChatGPTって、自信満々で間違ったことも言ってくるんですよね(笑)
だからこそ、ここは絶対に押さえておきたい。
✅ なぜChatGPTは嘘をつくのか?: AIは学習データに基づいて文章を生成するため、データに偏りがあったり、不正確な情報が含まれていたりすると、誤った内容を出力することがあります。「AIが出力した情報は鵜呑みにせず、必ず自分でファクトチェックをする」という意識を持つようになりました。
✅ Web検索と何が違うのか?: Web検索は既存の情報を探し出すのに対し、AIは与えられた情報や学習データに基づいて新しいテキストを生成します。この違いを理解することで、情報収集とコンテンツ作成でAIをどのように使い分けるべきか、戦略的に考えられるようになりました。
✅ 情報漏洩の心配はないのか?: OpenAIのプライバシーポリシーなどを確認し、機密性の高い情報を入力する際には注意が必要であることを学びました。公開しても問題のない範囲でAIを活用するという線引きを意識するようになりました。
この3つを理解すると、「このAIにどう頼ればいいか?」の設計が明確になり、プロンプトの書き方も格段に変わってきます。
例えば、「〇〇について、最新の信頼できる情報源に基づいて説明してください」のように、より具体的な指示を出すことで、AIの出力精度を高めることができるようになりました。
ステップ⑤:GPTsやExcelマクロに“触れてみる”
「ここまでやったら応用に行こう」と思っていた僕は、
いよいよGPTs(自作AI)に挑戦しました。
- 自分専用のライティング特化AIを作ってみたり
- ExcelのマクロをChatGPTに教えてもらいながら組んだり
…正直、最初は意味不明でした。
でもChatGPTに「初心者向けに分かりやすく教えて」と頼むと、
本当に1から順に説明してくれる。
“誰かに教えてもらう”の感覚で学べる。
これが、AIを使う一番のメリットなのかもしれません。
ステップ⑥:自分の仕事に落とし込む

ここまでやって初めて、「じゃあ自分の情報発信にどう使うか?」が明確に見えてきました。
僕はこんなふうにAIを活用しています:
✅ ブログ記事の構成案を複数提案してもらう: テーマとキーワードを伝えるだけで、様々な角度からの構成案が提示され、企画の幅が広がりました。
✅ 記事の見出しや導入文案を生成してもらう: 読者の興味を引くキャッチーな見出しや、記事の導入部分のいくつかのパターンをAIに作成してもらうことで、執筆の時間を大幅に短縮できました。
✅ 読者からの質問への返信文案を作成してもらう: よくある質問とその回答のテンプレートをAIに作成してもらい、返信にかかる時間を削減しました。
✅ 過去記事の分析と改善提案をしてもらう: 過去に書いた記事のアクセス状況や読者の反応を分析してもらい、改善点やリライトの方向性を提案してもらうことで、コンテンツの質向上に役立てています。
最初から「自分の業務にAIをどう使うか?」と考えても、なかなか具体的なアイデアは浮かびません。でも、この6ステップを踏むことで、「使える前提」がちゃんと整い、自然と自分の情報発信のフローにAIを組み込むことができるようになりました。
結論:「3時間」で“土台”は作れる
この6ステップを、僕は集中的に3時間ほどで試しました。ノンストップで一つずつ実践していくうちに、気づけばChatGPTが完全に“情報発信の戦力”になっていたのです。
もちろん、たった3時間でAIを完全にマスターできるわけではありません。しかし、「ちゃんと使える人間になった」と胸を張れるだけの確かな土台を築くことは十分に可能です。
さあ、あなたもAIという新しい相棒と共に、時間と可能性を広げる一歩を踏み出してみませんか? きっと、これまで想像もしなかった景色が広がっているはずです。
【特典】ブログ読者限定で『生成AI副業の教科書』を無料プレゼント!
今回ご紹介した内容は、僕自身が「人生を変えた」と断言できるノウハウのごく一部です。
実は、このノウハウを“1冊の書籍”にぎゅっと凝縮した
📘『AI副業の教科書』を、現在Kindleで【有料販売】しています。
ですが…
ここまで真剣に読んでくれたあなたには、特別に無料でプレゼントさせてください!
▼▼ 今すぐ無料で受け取る ▼▼